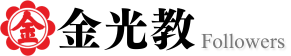【巻頭言】先人の祈りとお働きの中で

秋のご霊祭の月を迎えました。幽界ながらに私たちを守り導いてくださるご霊神様方のお働きに思いを致し、感謝の誠をささげたく存じます。
金光図書館も、この道の信心を受け継ぎ、現してくださった、多くの先人の祈りとお働きの中で、昭和18(1943)年9月8日に岡山県の認可を受け、昭和22年5月5日に開館しました。同年刊行された金光図書館報『土』には、初代図書館長金光鑑太郎様が、次のように「発刊の辞」を記しておられます。
「日本が、世界に寄与する文化圏となるためには色々大切なことがあるであろう。図書館もその一つとして考えられる。日本の中に図書館が一つふえた。その名を金光図書館という。大きくいえば世界に図書館の数が一つふえたことになる。図書館のための図書館では意味がない。利用され、活用され、生きてお役に立つ図書館でなくてはならない。金光図書館が出来て大助かりですといわれる。助かるといわれることは図書館が役に立つからである。役に立たないものはじゃまになる道理。この図書館が役に立つための一つのこととして、ここに図書館報『土』を発行する」
開館直後、5月の利用者数は、館内閲覧1889人、館外貸出78人、閲覧貸出冊数3123冊と記録されています。この数字からも、当時いかに人々が本を求めていたかが伺われます。さらに開館してみて分かったことは、利用者の大半が学生であったことです。当時は、学校図書館がほとんど整備されておらず、金光中学はもとより、倉敷市内の小中学校の生徒たちが、放課後に50~60人の一団となって来館しました。しかし、開館当初は小学生の利用を予想しておらず、児童書がありませんでした。そのため館長自ら、岡山へ出向き、大人向けの蔵書数冊と児童書1冊を交換してもらうこともあったといいます。
そのような時代を経て、昼夜を問わず情報が飛び交う今のこの社会において、「本」はどのような役割を担っているのでしょうか。ある文芸評論家は、「静かに本に向き合い、自分と対話をすることが、読書の大切な点である」と述べています。読書の楽しみ方は人それぞれですが、いつもより少しだけ世界に深く思いを巡らせ、新たな自分に出会うことも、その一つではないでしょうか。こうして私たちが本と向き合い、自分と向き合う時を得られるのも、先人方の祈りと尽力という、確かな土台があってこそです。その積み重ねの上で、「神様と共にある自分」を見いだしてゆく。そのような歩みの一助として、金光図書館がこれからもお役に立つことができればありがたく思います。
金光図書館長 高橋浩一郎