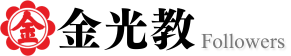【巻頭言】春の日差しのように

本教が一教独立を果たす以前のことです。教祖様ご帰幽から2年後の明治18(1885)年、本教は神道金光教会を設立し、神道事務局(後の神道本局)に属する教会として布教の公認を得ました。しかし、その体制の下では神道本局の強い影響を受け、教祖様の教えをそのまま説くことができなかったため、一教独立を求めての歩みを進めていくこととなりました。
そうした神道金光教会時代の話です。「神道金光教会規約」には「祭典」の項目に「4月9日10日 教会大祭」との規定があります。この規約が認可されたのが6月2日であることから、実際にこの規定に基づく「教会大祭」が執り行われたのは明治19年からと考えられます。このことから、私たちが現在「天地金乃神大祭」と称してお仕えさせていただいている春のご大祭は、明治19年前後から、「教会大祭」として執り行われていたのではないでしょうか。後に安田好三元教監が、「春の祭事は、本教が神道金光教会として教団の体をなしてから、天地の親神さまのおまつり、天地金乃神さまのおまつりとして仕えられてきたのである」と述べられていることからもそのように推察されます。
また、宿老・佐藤範雄師は、当時のことを振り返り、「道が拡がったその成績を語り合う感謝の大祭であった」と述懐され、明治19、20年当時のことについて次のように述べられています。
「教会長教師が話をしあって管長様へ本年度の教勢教義を打ち合わせたが、その以後は信者がだんだんついて参るようになり、会議が出来ないようになった。会議ができぬようになったことは大祭が盛んになったことである。(中略)各地にある教会もこれにならい話をし会議をするということが神の御心に通ったことでありまして、斯様な盛大な大祭になったことを皆承知しておかれたい」(「金光教徒」大正14年4月3日号)
このように春のご大祭は、教会長・教師が集まり、天地の親神様の御徳をたたえ、感謝を申し上げ、このお道の教えが各地に広がった喜びを語り合う大祭でした。そして、そうした喜びがどんどんと広がり、教会長教師が会議をできなくなるほど、共にご霊地に参拝する人々が増え、喜びを語り合うことになっていき、今日のようなご大祭が仕えられるようになったということです。
ご本部参拝のことを「お礼参拝」とも言います。この「お礼」には、「信心の喜びを語り合う」という意味が込められているのだと思います。これまで蒙ってきたおかげを持ち寄り、喜びと感謝の心をもって語り、伝え、さらにその喜びの輪が、春の日差しのように柔らかく、暖かく、そして力強く広がっていく――これが神様の御心に通じることであると宿老が教えてくださっています。春のご大祭の始まりに思いをいたし、当初からつながってきた喜びの輪がさらに広がっていくような信心の実践を求め現してまいりたいと思います。
財務部長 橋本信一