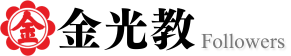【巻頭言】教祖を拝し奉るの気持ちになって

今年、20数年振りに御霊地でお正月を迎えました。境内に、「謹賀新年」の幟が立ち並ぶ中、全国各地から本部広前へ年賀参拝に訪れる方々の姿を拝ませていただいていた時のことです。
境内の願い礼記入所では、参拝者が自由に持ち帰ることのできる「み教え短冊」が並べられており、ある初老の男性が、それをじっと眺めながら、「何やこれ、全部当たり前のことが書いとるのぉ」とつぶやかれました。とっさの一言に驚きましたが、そばにいた本部職員が「そうですねぇ。その当たり前のことがなかなかできないお互いですから、日々の稽古が要るんですよねぇ」と返答したところ、男性は「…ほんと、そうじゃのう」と得心された様子で、選んだ短冊を手に、会堂へ向かわれました。
教祖様のみ教えは、誰もが分かる平易な言葉で語られています。しかし、「分かること」と「できること」、「知っていること」と「身に付いていること」は果たして一致しているでしょうか。正月早々、手元足下を見つめ直したいと、思いを新たにさせていただきました。
『金光教教典』の「内伝」には、佐藤範雄師が次のように書かれています。
「先日も、道のことに志の篤い青年が来て、教えを受けたいと言う。忙しくしておる時で、会って話してやることができない。幸い、その青年の問うことは、かねて文書にしておったから、これを読んでみよと言って出してやったら、五分間ほどで読んで返しに来た。それは、五分間もあれば読むことは読めるのだが、しかし、その中に書いてあることは私より他に知る者はないので、それを読んで当時を追想し熟考し黙想せば、一時間や二時間くらい動けるものではない。それを五分間ほどで読んで、すぐに返して来た。それで、文書をもってする教えは大いに考えものだという気がした。それを読んでは、しばらく涙を流して動くこともできぬくらいのものと、私は思うておったのである。
書いてある物も、教祖のことを書いてある物は、教祖を拝し奉るの気持ちになって拝見すること大切なり。そこに道力が備わるなり」
ここでの佐藤範雄師と青年との違いは何でしょうか。同じ書かれたものであっても、その向き合い方や頂き方、求道の熱意によって天と地ほどの違いが生まれてしまいます。
「しばらく涙を流して動くこともできぬくらいのもの」に触れていながら、私自身、粗末な頂き方になっていないだろうかと自省しつつ、「教祖を拝し奉るの気持ちになって拝見する」という中身を日々求めていきたいと願います。
布教部長 塚本一眞