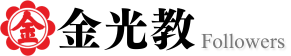祈りでつくる小さな居場所【金光新聞】
子どもたちが抱える「しんどさ」に耳を傾ける
私は3年前から、高校内に設けられた「居場所カフェ」でスタッフをしている。
今、日本の子どもの7人に1人は、貧困の状態にあるといわれる。現代の貧困は見えにくいといわれるが、子どもたちと接していれば、貧困が「見える」。子どもたちと接していて思うのは、関係性から生まれる居場所があることの大切さである。
大阪府は高校中退率が全国で一番高く、その打開策の一つとして、「居場所カフェ」が生まれた。問題を抱えた生徒の存在に早く気付ければ解決の糸口が見つかるかもしれない、という願いからだ。
昼休みと放課後、ココアや抹茶ラテなどを用意して、子どもたちが来るのを待つ。チャイムが鳴ると、大抵最初に来るのはいつも独りぼっちの3年生。続いて幾つものグループがやって来る。1日40人近くが来店し、とてもにぎやかだ。
私は、カフェで次の七つのことを心掛けて話を聴いている。それは、「できるだけ関心を持つ」 「話の腰を折らない」 「責めない」 「ばかにしない」 「うそをつかない」 「驚き過ぎない」 「尋ねられたら、自分のことも言える範囲で答える」ということである。
子どもたちと接していると、家庭生活での余裕のなさを感じることがある。まず、食事。昼食がスナック菓子やコンビニなどのポテトフライだけという子、弁当を持ってきていない子もいる。身だしなみについても、ワイシャツの襟や袖がいつも真っ黒な子がいる。
ある時、カフェに来た子たちがこんな話をしていた。ある女の子が、 「風邪をひいて学校を休んでも、バイトは休めない」と言うと、多くの子が「そうそう」とうなずいていた。家計を助けるためにバイトをしている子がかなり多いのだ。これでは、進学のための勉強はままならず、貧困の連鎖を断ち切れない。
カフェを 「自分の居場所」にしている子どもの中には、 貧困ももちろんそうだが、それ以外にも何かしらの「しんどさ」を抱えている子が多い。家庭環境の複雑さ、発達障害、国籍、性的マイノリティーなどなど。さらに、親からの暴言・暴力、 無関心(ネグレクト)。家が安心できる居場所でないことは珍しくない。カフェでは、子どもが深刻な状況に置かれていないか、スタッフ同士ひそかにアンテナを張りながら話に耳を傾けている。もし重大な問題があれば、学校の先生方と情報を共有し、場合によっては解決に向けた行動につなげていく。
とはいえ、子どもたちはなかなかその「しんどさ」を語ろうとはしない。わが家の窮状を他人に話すのは恥ずかしいだろうし、親のことも悪く言いたくない気持ちもあるだろう。それでも、何げない会話の中で、時々ぽろっとこぼれ落ちるように、「しんどさ」が語られるのだ。いじめ、過去に受けた虐待の記憶、親のこと、障害のこと…。そんな時は、全身を耳にして、聴かせてもらう。
私は居場所カフェに向かう前、「どうぞ必要な子をカフェにお引き寄せください。必要なことを聞かせてください。そして神様のような温かい言葉を掛けさせてください」と、神様に祈る。そして、カフェでは子どもたちが直面する厳しい現実に耳を傾け、心の中で神様がお働きくださるのをただただ願っている。
皆さんの周りにも、きっと「しんどい」状況を抱えた子がいるはずだ。例えば、朝、家の前を掃除する時など、登校する子どもたちに、ぜひ、祈りのこもったあいさつや言葉を掛けてあげてほしい。ささやかな一言が励みになり、そこに生まれた関係性が小さな居場所をつくることになるかもしれない。